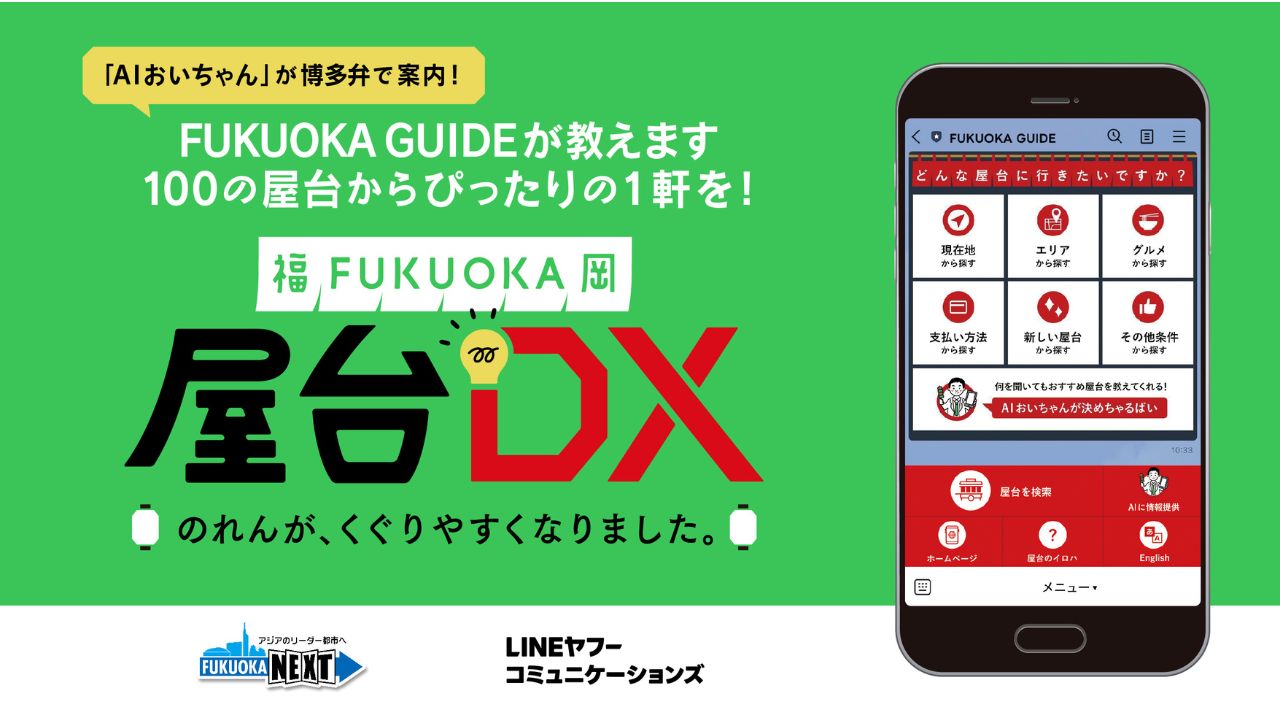総務大臣賞/ACCグランプリ
%e9%87%91%e9%be%8d_KV_16-9.jpg)
- 作品名
- 道頓堀 金龍のしっぽ Project
- 審査評
-
撤去を観光資源にしたアイデア。くいだおれ人形のように撤去を話題にしたアイデアは過去にもあったが、「ないこと」を永続的な集客装置に変えている点は特筆すべきだし、お向かいの「かに」を巻き込んだことで、一店舗の施策を超え、街の物語にしたことも素晴らしい。またこの時代にデジタルやソーシャルの「お作法」をほぼ使わず、アイデアで一点突破したことも、今後のプロモーションアイデアを考える手本になるだろう。PRではないか?という声もあったが、批判を好意に変え、未来の顧客離れを回避した点で十分なプロモーションだろう。
(小西 利行)金龍の仕事は、企画者の従来の王道の広告クリエイティブとは異なるプロモーション/アクティベーション領域の強みを最大限に活かしつつ、殺伐とした時代を象徴する瞬間に関西らしい愉快なアイデアを添えるジャーナリスティックな切り口に、自分から飛び込んでいって結果を出すプロデューサー的な勇気も持ち合わせていて、その表現は極めてチャーミング。審査委員誰も文句なしの受賞だったように思います。事件現場のせいで、一瞬大名作「消えたかに道楽」が頭を過ぎる点だけ議論を呼び、そこは気の毒ではありました。
(菅野 薫)建造物の撤去命令を「龍のしっぽが切られた」というストーリーに変換し、訴訟という大人同士の争いを大阪らしい笑いに昇華、さらに金龍の宣伝に結びつけた卓越したプロモーション施策。本来、裁判による係争はブランドにもお客さまにとっても笑い話にはならない。しかし本施策は、クリエイティブコミュニケーションによってお店のプロモーションに逆転させ、まさに“拳の下ろし方”の妙を示している。国内全体を巻き込む大規模キャンペーンではないものの、課題の着眼点からアウトプットの精緻さに至るまで、プロモーション/アクティベーションの”真髄”が凝縮されたグランプリにふさわしい業務。
(畑中 翔太)僕は心斎橋付近に住んでいたこともありこの辺りの空気感もなんとなくわかるのですが「もしこの企画がなかったら、この金龍ラーメン、(商店街の空気的に)結構居づらかったんじゃないかなあ」と予想できます。そんな状況をアイデアとちょっとのユーモアで逆転させたのが鮮やかですし、どうやら自主提案だった(?)という話も聞き、広告プランナーとしては見習わねばと思いました。
(花田 礼)うおーすごすぎるーっって思った企画です!「良いアイデアがあれば、なんだって突破できる」をまさに体現している仕事で、グランプリに相応しいと思いました!「金龍の騒動をニュースで見て、あなたならどう動きますか?」自分は何も出来ませんでした!すごいです、おめでとうございます!
(明円 卓)








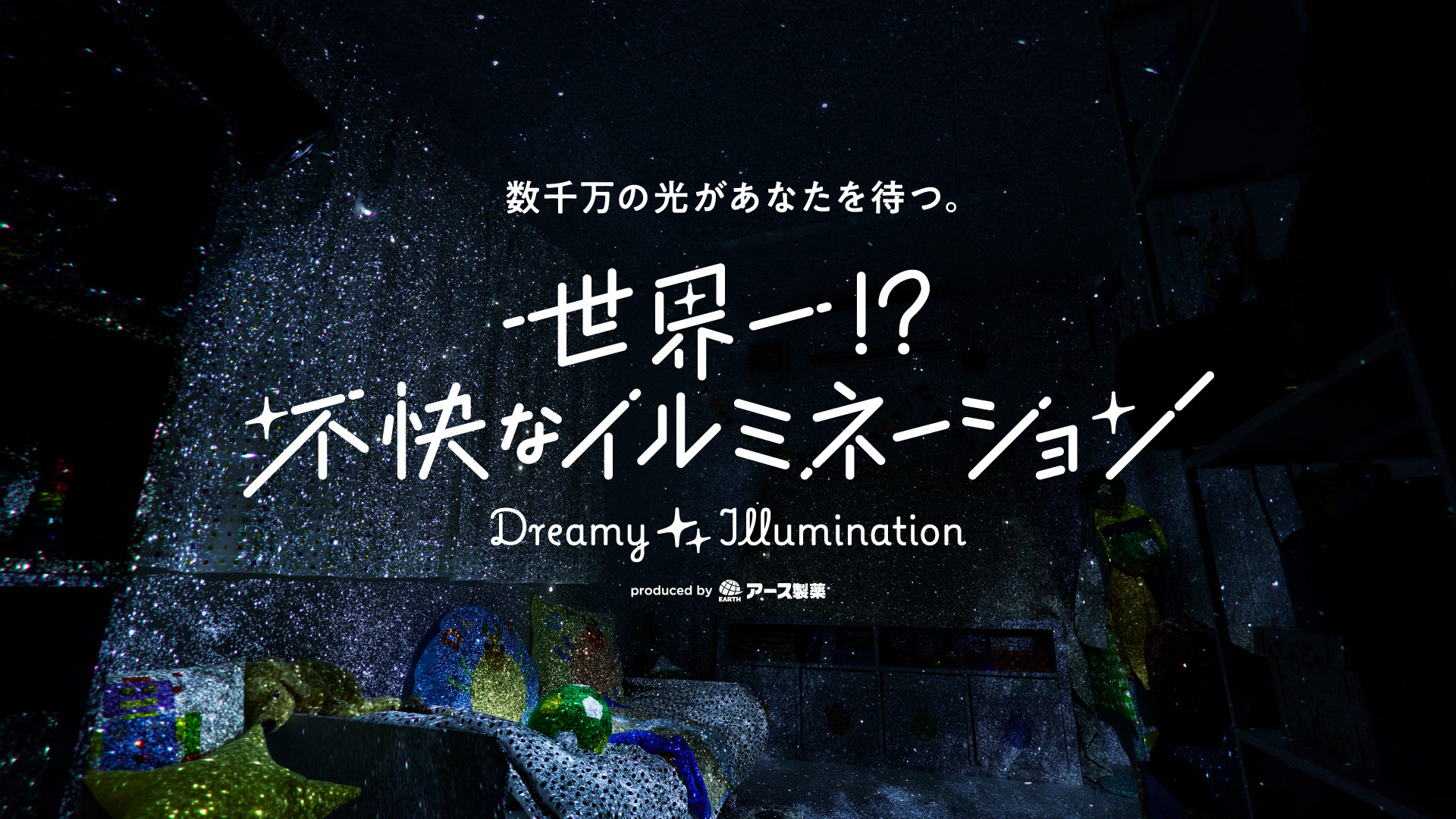


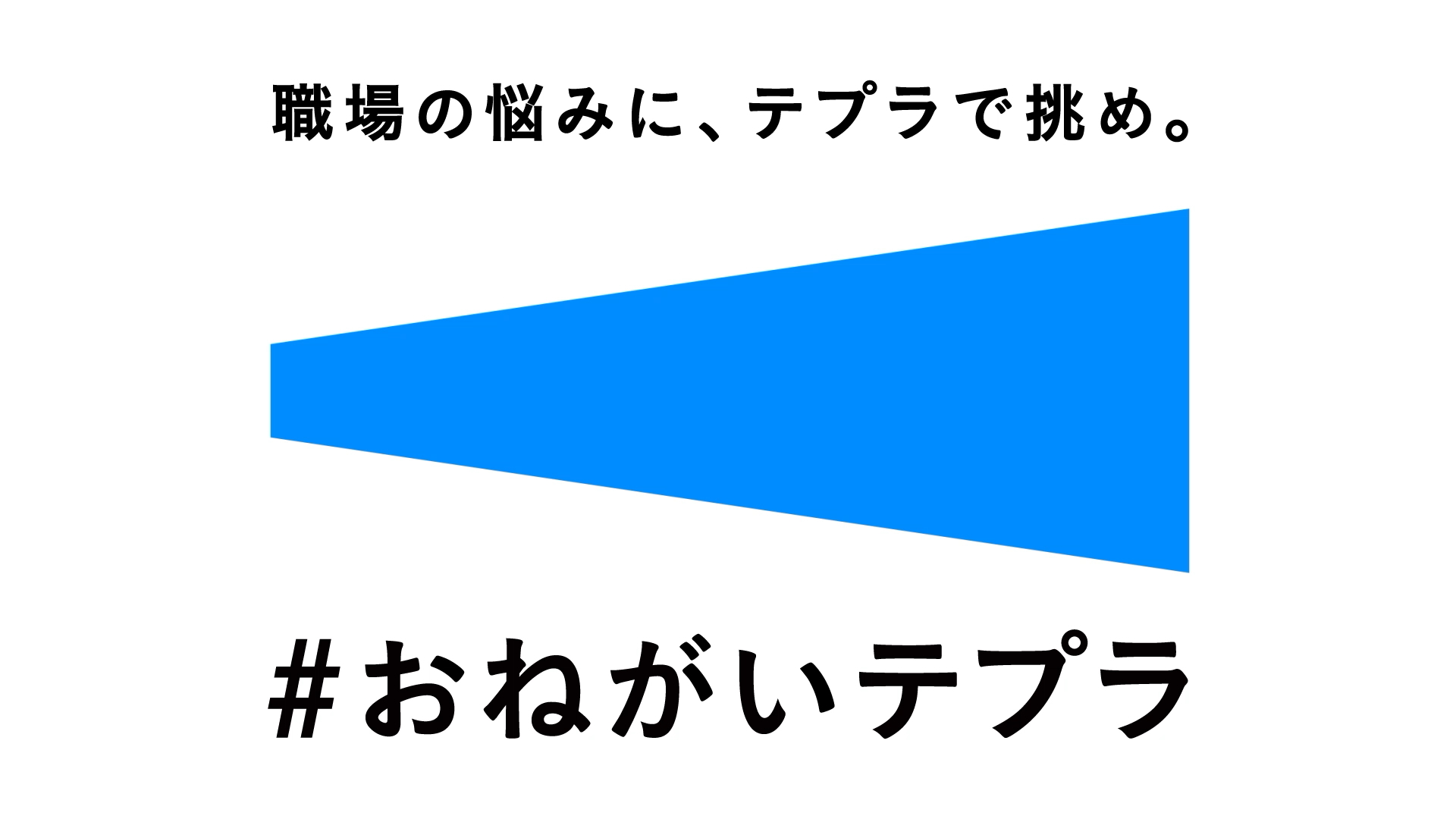




%e6%81%a9%e4%ba%ba%e6%8e%a2%e3%81%97%e7%94%bb%e5%83%8f.jpeg)

%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e8%a3%bd%e8%96%ac%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e7%94%bb%e9%9d%a2.jpg)








%e5%a4%a7%e5%a1%9a%e8%a3%bd%e8%96%ac%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e7%94%bb%e9%9d%a2.jpg)