第4回 クリエイターズ殿堂

- 選考理由
-
トリローグループの一員となり、野坂昭如氏らと組んで多くのCMソングを作曲した。特に、名作と言われた明治製菓(当時)の「チョコレートの唄」はACC賞ラジオCM部門のグランプリを受賞し、現在でもCMソングとして使われている。また、テレビのCM映像と音楽という面でも、CMに強い情緒性を与える新しい試みを続けた。後に「オールスタッフ」を設立し、多くのCM作曲家を育てた。さまざまなジャンルでヒットソングを数多く生み、やがてミュージカルの育成も目指したが、62歳で没した。
- プロフィール
- 1930(昭和5)年東京市下谷区谷中生まれ。1946(昭和21)年、第一期生として鎌倉アカデミア演劇科に入学。卒業後、ダンプカーの運転手などをしながら芥川也寸志氏に師事し作曲活動を始める。後に三木鶏郎氏が率いる「冗談工房」に参加し、歌謡曲から、フォークソング、CMソング、アニメソング、ミュージカル、交響曲と幅広いジャンルの曲を作曲。総数は15,000曲にも上る。1969(昭和44)年には佐良直美氏の「いいじゃないの幸せならば」が第11回日本レコード大賞を受賞。「歌はドラマである」という自らのモットーに基づいて、「見上げてごらん夜の星を」、「おれたちは天使じゃない」など多数のミュージカルも手掛けた。ACC賞は1966(昭和41)年、明治製菓(当時)「明治チョコレートのテーマ」でラジオCM部門のグランプリを受賞。他にも多数受賞。1992(平成4)年5月肝不全のため逝去。62歳

- 選考理由
-
番組よりCMが面白いと言われた「日曜洋画劇場」の中で放映された東條忠義氏のサントリーのCMは、「60秒のエッセイ」と言われ、多くの人たちから人気があった。「開高健よりも開高らしく、山口瞳よりも山口らしい」と言われた氏のコピーは人間の機微の不思議や面白さを、わずか60秒の世界で見事に描いてみせた。知的なエンターティメントを究めた人であった。「CMは文化だ」と、世の中の人たちに認めさせた人でもあった。
- プロフィール
- 1938(昭和13)年岩手県生まれ。同志社大学を中退、武蔵野美術短期大学入学・卒業後、日本テレビジョンに入社。1964(昭和39)年創業間もないサン・アドに転向後、開高健氏、山口瞳氏らの知識人の出演を得ながら、「文学CM」と言われていたサントリーの多くのCMを手掛けた。原点に東條氏自身の生活そのものがあり、それを自然に描くような作風であった。フリーになってからも資生堂「タクティクス」等数多くのCMを企画・演出。ACC賞は1974(昭和49)年サントリー角瓶「雁風呂」、1985(昭和60)年サントリーオールド「FRIENDS」でテレビCM部門グランプリ、特別賞(コピー賞)等を獲得するなど多数受賞。絵画、陶芸、家具などにも造詣が深く、個展も開催。2007(平成19)年69歳で逝去。

- 選考理由
-
さまざまなスタッフを使いながら、ACC賞のラジオCM部門で13年間で11回グランプリを獲り続けた偉業を達成。少なくとも、中心のアイディアは堀川靖晃氏がコントロールしていて、ラジオCMの表現の極致を常に目指していた。現在でも、パナソニックがラジオCMの力を信じ、ラジオの新しい表現に挑んでいるのは、氏の培ったものが生きているからなのだろう。
- プロフィール
- 元松下電器産業(当時)宣伝事業部、元宝塚造形芸術大学専門職大学院教授。1964(昭和39)年入社。1969(昭和44)年、松下電器産業(同)「ナショナルステレオ虫の音」でACC賞ラジオCM部門グランプリを受賞したのを皮切りに、同部門では13年間に11回のグランプリを獲得。1971年のフジサンケイグループ広告大賞のグランプリはマスコミ4媒体にメディアミックスを加えた5部門それぞれの最優秀作品で競う枠組みであったが、ラジオCM「ナショナル浄水器水の旅」(同年のACC賞ラジオCM部門グランプリ)が他の4部門を押さえて受賞。1983(昭和58)年には「テクニクスEXE原音の心シリーズ」でテレビCM部門全日本フィルムCM大賞も受賞。1981(昭和56)年度第15回大阪広告協会「やってみなはれ佐治敬三賞」を「堀川靖晃とラジオCM制作グループ」として受賞。72歳。
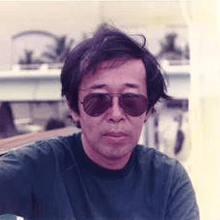
- 選考理由
-
初期のテレビCMは、カメラと照明は完全に分業化されており、全体のトーン&マナーの決定者は誰であるのかはっきりしていなかった。やがて、スチールカメラマンの参入が盛んになると彼らは照明の設計も、当然のように自分で行うようになった。撮影の規模が大きくなったり、人物の動きがダイナミックなものになると、分業としての照明が必要となり、スチールカメラマンの意図を理解し、実行できる照明マンが必要となった。そこに登場したのが、髙宮丈夫氏だった。もちろん、間接照明など、グラフィックな映像に近づく試みをしてきた照明マンは、それまでにもいなかったわけではない。しかし、照明マンが単独に「才能」として業界の人々の話題になったのは髙宮氏が初めてだと思う。影を消すたびに、ライトがまたひとつ増えて行くという、ハリウッドスタイルのはん雑な照明から、むしろ陰影こそが美しいというCM独自の映像を確かなものにした氏の革新性は今でも日本のCMの中に生きている。
- プロフィール
- 1931(昭和6)年9月5日生まれ。東京都世田谷区出身。私立麻布高校卒業。1963(昭和38)年頃から日本天然色映画にてライトマンとして活躍。1969(昭和44)年杉山登志氏と組んだ資生堂「サンオイル」、帝人「水着」でACC賞テレビCM部門金賞受賞。以後毎年の様に秀作賞などを受賞。1979(昭和54)年には松下電器産業(当時)「自転車、特訓」でACC賞全日本CM大賞受賞。サントリー、レナウン、味の素等数々の名作のライティングを担当。後進も多数育成した。1995(平成7)年63歳で逝去。
【第4回クリエイターズ殿堂 選考委員】(五十音順)
- ■ 選考委員長
小田桐 昭氏 - ■ 選考委員
坂田 耕、杉山 恒太郎、武部 守晃、宮崎 晋の各氏




